
\気軽に無料相談/
\日々の情報発信/


人が亡くなり相続が開始すると、その相続人は、現預金や不動産などの価値のある財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継してしまいます。遺産の中に特に価値のあるものが無く、借金ばかりあるような場合でも、その相続人が全て引継ぎ、清算しなければならないとすると、相続人にとってあまりにも酷な結果となってしまいます。
そこで現代の民法では相続放棄という選択肢が用意され、民法939条は「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と述べています。
大昔の家督相続という制度の下においては、法定家督相続人が家の財産を全て一人で相続すると定められ、その放棄をすることは許されていませんでした(旧民法1020条)。そこには、親の負債を子が返す父債子還という儒教精神が関係しています。
個人の尊厳と法の下の平等という基本理念を持つ日本国憲法が施行された現行相続法の下では、家督相続制度は完全に廃止され、個人主義・私的自治の精神の下、相続人に与えられた相続放棄という選択肢は、とても重要な意味を持っています。

‘‘民法第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。【後略】‘‘
‘‘民法第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。‘‘
具体的には、管轄の家庭裁判所(原則、被相続人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所、家事事件手続法201条①、民法883条)に「相続放棄申述書」と戸籍謄本等を提出して行います。管轄家庭裁判所が遠方である場合には、郵送で提出することも可能です。
相続放棄の申述は、原則申述人本人の意思によって行われることが必要です。身体障害や高齢であるために、申述書に自筆できない場合などに本人から頼まれて他者が代筆すること自体は可能ですが、本人の意思によらず、勝手に手続をすることはできません。本人が認知症や障害により、手続を理解することができなければ、成年後見制度の利用の検討が必要です。
本人に成年後見人や、相続放棄の代理権を有した保佐人・補助人が就任している場合は、成年後見人・保佐人・補助人の代理による相続放棄も可能です。

‘‘民法第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。‘‘
家庭裁判所において、相続放棄の申述が受理されると、その相続人は初めから相続人でなかったものとして扱われます。要するに、現預金や不動産などの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も引き継がないことになりますので、たとえ親の借金であっても、(相続人自身が保証人などでない限り)法律上、債権者に弁済する義務はありません。

‘‘民法第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。【後略】。‘‘

相続放棄ができる3か月の期間を「熟慮期間」といいます。相続人は、相続をするか放棄をするかの判断をするために、相続財産の内容を調査する必要があります。しかし、この期間が必要以上に長ければ、相続債権者(例えば、被相続人にお金を貸していた者)は、相続人に対して債権を行使できるのか否か不確定の状況が続いてしまい、不利益を被ってしまいます。よって、熟慮期間は3か月と定められ、この期間内に限定承認又は相続放棄がなされなかった場合は、相続を承認したものとみなされます(法定単純承認:§921二)。

熟慮期間の始点は上記の条文において「自己のために相続の開始があったことを知った時」とされていますが、この起算点がいつになるかの解釈は、非常に難しいものです。
大昔の大審院(現在の最高裁判所の前身)という機関の判断では、①相続開始原因(被相続人の死亡又は失踪宣告)②自分が相続人になったことを知った時とされていました(大決大正15.8.3)。しかし、この解釈によると、例えば相続する遺産が全くないと認識しており、その間に3か月の熟慮期間が経過してしまった後、予期しない借金などが判明した場合には、相続人にとっては不測の不利益となってしまいます。
そこで後に現れる昭和59年判決(最判昭和59.4.27)は、一定の場合に熟慮期間の起算点の繰り下げを認める解釈を示します。すなわち、上記で示した①②の事実を知っている場合でも、被相続人に相続財産が無いと誤信し、かつ、生前被相続人と交流がなかったなどの事情があり、そのように誤信してしまう相当な理由が認められる場合には、熟慮期間は相続財産を認識した時(例えば、後から借金の請求をされ、債務を認識した時)から起算すべきとされています。
他にも、一旦遺産分割を行ってしまった後の相続放棄が認められた事例(大阪高決平成10.2.9)、相続債権者が誤った回答をしたために相続人が相続財産に債務がないと誤認してしまった場合に放棄が認められた事例(高松高決平成20.3.5)などがあります。

相続人が複数人である共同相続の場合、各相続人の熟慮期間は個別に開始します。熟慮期間の始点はあくまで「自己のために」相続の開始があったことを知った時から三箇月以内、となっていますので、客観的な事実や他の相続人の事情は無関係であり、相続人ごとにその熟慮期間の起算点は異なることがあります。
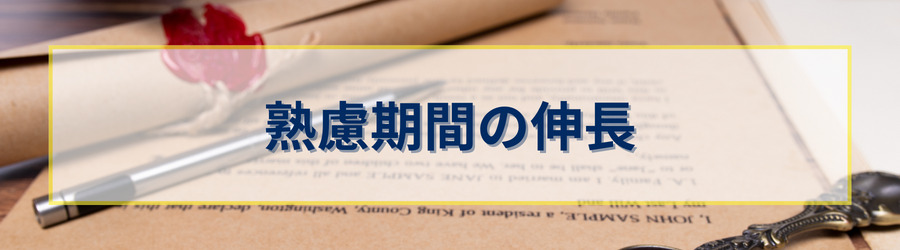
‘‘民法第915条 【前略】ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。【後略】‘‘
例えば、相続財産が多額である場合や相続債務の種類が多岐にわたっている場合、相続人が海外にいる場合などは、相続財産の調査が難航することが予想され、3か月以上の期間を要する場合も考えられます。そのような事情にも関わらず熟慮期間を一律3か月と定めることは不合理であるため、民法は一定の場合に熟慮期間の伸長を認めました。
請求権者は利害関係人又は検察官とされていますが、現実的には相続人が自己の熟慮期間の伸長を求める事例がほとんどでしょう。伸長の手続は、家庭裁判所に対する申立てによって行います。
当然のことですが、熟慮期間の伸長の申立ては熟慮期間内に行う必要があります。熟慮期間経過後に伸長の申立てを行いこれが認められるとすれば、債権者の保護という熟慮期間の持つ役割が薄くなってしまいます。
伸長できる回数に制限はありません。ただし、2回目以降の伸長申立てに対しては家庭裁判所も慎重になることが多いと思われるため、伸長が必要な事情について何らかの疎明が必要になる場合もあります。
伸長される期間は家庭裁判所の判断になりますが、特段長期の伸長の必要性が見込まれない事例では3か月とされる事例が多いとされています。
なお、熟慮期間の伸長の手続は数週間から1か月程度かかることが多いと思われます。それでは申立ては熟慮期間内に行われたものの、伸長の審判が熟慮期間内に間に合わなかった場合はどうでしょうか。この場合においても、期間伸長の審判を行うことは問題ないとされています。熟慮期間内に申立てが間に合ったのであれば、その後の事務手続にかかる期間は裁判所の都合ですので、当然の結論でしょう。
熟慮期間の経過後に申立てが却下される場合はどうなるでしょうか。申立て時は熟慮期間内であるためその時点では相続放棄という選択肢があったにも関わらず、伸長の却下審判時には熟慮期間が経過してしまっている場合は、その審判が確定すると同時に法定単純承認となってしまうことに留意が必要です(§921二)。この場合には、かかる相続人の不利益を回避するため、期間伸長の事由を欠いているとしても、却下審判をせず1週間から10日程度の短期間の伸長を認めて、相続放棄又は限定承認の機会を与えることが相当とする説もあります。
〒060-0062
北海道札幌市中央区南2条西9丁目1番地11
カサトレスネオ505号
TEL:011-522-9184
営業時間:10時〜19時
定休日:日曜日
代表者:木下 涼太/藤原 徳喜雄