
\気軽に無料相談/
\日々の情報発信/

死亡危急者遺言は、死亡危急時遺言や一般危急時遺言とも呼ばれ、細かい作成条件は後述しますが、その名のとおり遺言者に死が迫った状況下においてのみ許される方式の遺言です。そのような差し迫った状況における方式のため、遺言者が口頭によって遺言を残すことができる点では簡易な方式といえますが、その一方で、証人についてや家庭裁判所における確認手続など、自筆証書遺言や公正証書遺言にはない厳格な方式が要求されています。

一見利用される状況が想像しにくい方式ですが、死亡危急者遺言の要件の一つである「疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者」という方式は比較的緩やかに解されており、利用可能な状況は現実にも多く存在すると考えられます。
以下、民法の規定に沿って死亡危急者遺言の要件、作成手順等を解説します。この方式は特殊な状況下において遺言者の口頭による遺言を例外的に認めたものであることから、証人や家庭裁判所での確認手続については厳しい要件が要求されるほか、作成直後に遺言者が死亡することも考えられ、方式に誤りがあった場合は取り返しがつかないリスクのある方式ともいえます。万が一利用が想定される状況になった際には、専門家への相談が必須となるでしょう。

死亡危急者遺言の民法の条文は下記になります。以下、それぞれの要件について一つ一つ解説していきます。
‘‘民法第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。【第2項以降省略】‘‘
「疾病その他の事由」については、その原因について特に制約がありません。「疾病」というとガンなどの病気が想定されやすいですが、その他、受傷、老衰等によるものも考えられます。
死が急迫しているか否かの判断については、医学的な診断や客観性までは要求されず、主観的なもので良いとされています。遺言者自身が、自らに死亡の危険迫っていると感じるほどの自覚があれば、この方式によることが可能です。
公正証書遺言(§969)や秘密証書遺言(§970)では証人の数は二人以上とされており、民法に定められた遺言の方式の中で三人以上の証人を要求する方式はこの死亡危急者遺言ただ一つとなっています。
死亡危急者遺言は遺言者の口頭によることができるという簡易な方式を認めているため、遺言者の真意をより正確に伝達するため、他の方式よりも多い証人の数が要求されているものと考えられています。証人の数が多ければ、証人間で通謀して遺言内容の偽造を行うことが難しくなるという効果も期待できます。
遺言者は、上記3人の証人のうちの1人に、遺言の内容を口頭で伝えます。よって、自筆証書遺言のように自書する必要がないため、病気により体力がなくても、遺言を残すことができます。
上記により遺言者から口授を受けた証人は、遺言の内容を筆記します。この筆記については、遺言者が述べた内容を一言一句書き写す必要はなく、遺言の趣旨が明確になっていれば足りるとされています。
また筆記といっても、自筆証書遺言と異なり、手書きである必要はなく、パソコン等による入力でも構いません。
筆記をした証人は、遺言者及び他の証人にその内容を読み聞かせるか、閲覧をさせます。
上記による証人の1人によるの読み聞かせ又は閲覧の後、他の証人2人は筆記が正確なことを承認します。この際、遺言者本人の承認を得る必要はありません。これは、危急者遺言を利用する状況下では、遺言者自身に死亡の危急が切迫していることから承認を求め得ない場合も多いと想定されているためです。
証人による筆記の承認の後、全証人が署名・押印を行います。この場合も、上記と同様の理由で遺言者本人の署名・押印は必要ありません。
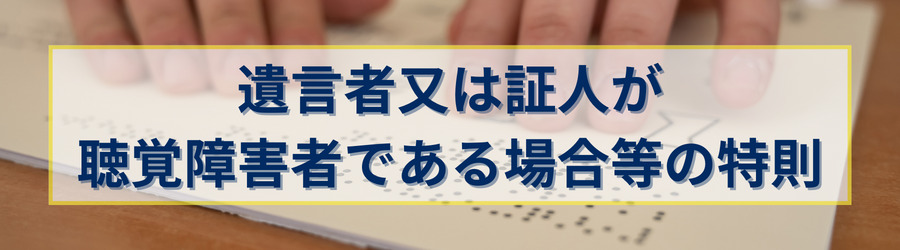
まず、遺言者が言語障害者である場合には、遺言の内容を証人に口授することができません。そのためその代替措置として、遺言者が証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳(手話通訳)を介して申述することにより、口授に代えることができるようになりました。この通訳人には手話通訳士などの資格は求められず、遺言者と意思疎通できる者であればよいとされています。
続いて、遺言者又は筆記する証人以外の証人が聴覚障害者である場合は、筆記した遺言の内容の読み聞かせを聴き取ることができません。その代替措置として、筆記した内容を通訳人の通訳により、読み聞かせに代えることができます。通訳人の注意事項については、上記と同じです。

死亡危急者遺言は、自筆証書遺言や公正証書遺言と異なり、遺言書を完成させただけでは有効となりません。家庭裁判所において「確認手続」をする必要があります。死亡危急者遺言は、遺言者本人に死亡の危急が迫った際に口頭による遺言を認めているという特殊性から、遺言の内容が遺言者の真意によるものかを確認する必要があるためです。この確認手続を経ない死亡危急者遺言は無効となってしまいます。
遺言の確認手続をするには、基本的に証人の1人が、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に申立てなければなりません。証人以外にも、相続人や受遺者なども、この確認手続の申立てをすることができるとされています。
20日を過ぎた申立ては原則として却下されることになりますが、期間内に申立てができなかった事情がある事例について、期間経過後の申立てを認めた裁判例が複数みられ、この要件については比較的緩やかに解されていると考えられます。
家庭裁判所における審理のポイントは、その遺言が遺言者の真意に基づくものか否かという点です。具体的には、家庭裁判所調査官が証人のほか、推定相続人や医療従事者、知人等から作成当時の状況や事情を聴取し行うことになると思われますが、申立時に遺言者本人が生存している場合には、調査官が本人のもとに出張し、面談することも考えられます。よって、法律上の申立期間は遺言の日から20日以内となっていますが、遺言者の真意を確認する方法としては、本人生存中に直接確認することが最善であることも多いと考えられるため、可能な限り遺言者生存中に申立てることが望ましいでしょう。
死亡危急者遺言は、上記の遺言の確認手続のほか、遺言書の検認の手続を経る必要があります。「確認」と「検認」の手続の違いについては、下記のとおりです。
遺言の確認(§976④)
申立期間:遺言の日から20日以内
手続の目的:遺言者の真意の確認
手続をしなかった場合:遺言が有効とならない
●遺言書の検認(§1004①)
申立期間:遅滞なく(明確な期限なし)
手続の目的:遺言書の偽造・変造の防止、相続人に遺言書の内容を知らせること
手続きをしなかった場合:遺言の効力には影響はない。ただし、検認が行われていない遺言書は、通常、金融機関の手続や不動産の名義変更に利用できない。
また、検認義務を果たさなかった者は、5万円以下の過料に処せられる。
死亡危急者遺言は、遺言者が普通の方式(自筆証書遺言や公正証書遺言)によって遺言をすることができるようになったときから時から6か月間生存したときは、無効となります。
死亡危急者遺言は、遺言者に死が迫っているという特殊な状況下において、一部要件を緩和した例外的な方式です。よって、一度死亡危急者遺言を作成した後であっても、通常通り自筆証書遺言や公正証書遺言が可能な状況が続いているのであれば、その方式により再度遺言をすればよく、死亡危急者遺言という例外的な方式を認める必要がなくなるため無効となります。
〒060-0062
北海道札幌市中央区南2条西9丁目1番地11
カサトレスネオ505号
TEL:011-522-9184
営業時間:10時〜17時
定休日:日曜日
代表者:木下 涼太/藤原 徳喜雄